ステップファミリー調査結果のご報告
特別推進プロジェクト「現代社会における技術と人間」
「ソーシャルサポートにおけるCMC」研究グループ
明治学院大学社会学部付属研究所
〒108-8636 東京都港区白金台 1-2-37
電話:03-5421-5204/ファックス:03-5421-5205(担当:森田・小林)
メールアドレス:stepfam@soc.meijigakuin.ac.jp
関連ホームページ:http://www.meijigakuin.ac.jp/~stepfam
2001年10月に開始した「ステップファミリーに関するアンケート調査」が本年5月末日で回答者の募集を終了いたしました。皆様のご協力に、あらためて御礼申し上げます。私たちは、今年2月22日までに回収した113人分のアンケート調査データ(うち郵送回答93人、メール回答20人)を分析してきました。その結果をまとめた報告書『ステップファミリーにおけるソーシャル・サポートの研究』の詳細は、当調査プロジェクトのホームページ(上記)でご覧いただけます。以下では、分析結果の一部を簡単にご報告いたします(ほぼ同様の内容がSAJのニュースレター『ステップファミリーズ』4号にも掲載されました)。私たちの調査研究は今後も継続する予定です。アンケートで今後のインタビュー調査にご協力いただけるとご回答いただいた方々には、こちらからご連絡を差し上げる場合があります。その折には、どうかご協力をよろしくお願い申し上げます。
2002年7月
1.回答いただいた方々の全体的特徴
はじめにお断りしておかなければいけないのは、この調査のデータが必ずしも日本のステップファミリーの全体像を代表しているとは言えないことです。日本で初めてのステップファミリー調査ということで、協力者を募る方法に苦労しました。昨年、翻訳出版されたヴィッシャー夫妻の著書『ステップファミリー』に挟み込んだ応募葉書のほか、講演会やウェブ上での募集となりました。通常の社会調査では、研究の対象となる人々の集団(母集団)全体からできるだけランダムに調査対象者を抽出し、代表的なサンプルを調査します。そうすることで全体(母集団)の様子を推定することができるのです。日本のステップファミリーに関してはそのような方法は不可能なので、今回のような方法を採らざるをえませんでした。したがって、今回の調査から得られた結果(具体的なパーセントなどの数値)が、そのままステップファミリー一般にあてはまるとか、確実に一般化できる結論だと考えるわけにはいきません。しかしながら、この試行的な調査の結果も、日本のステップファミリーを理解するための貴重な手がかりには違いありません。
今回の調査回答者の特徴は、(1)女性が圧倒的に多いこと(女性回答者83人に対して男性回答者30人)、(2)回答者のうち48人(24組)のカップル回答者を含んでいること、(3)プレステップを含む、ステップファミリーの初期段階にある人に偏っていること、などです。結婚年数4年以上の回答者は(未入籍者を含めた)全体の2割強(女性の23%、男性の17%)に過ぎず、結婚後1年未満の人が男女とも約2割を占めています。女性回答者の 23%、男性回答者の14%がパートナーとは(まだ)婚姻関係にないと回答しています。なお、女性の25%、男性の17%はパートナーと別居または半別居状態にあり、完全な同居生活が始まっていません。男性の年齢は平均39.4歳(29歳~69歳)、女性は平均34.3歳(22歳~60歳)でした。比較的若年で、ステップファミリーを始めたばかりの家族に偏っています。
2.家族内のストレスとパートナーとの関係
今回の調査では、家族やそれ以外の人間関係から生じるストレスや家族関係の満足感などについて、かなり詳しく訊いています。分析の結果からは、ステップファミリーにおける(継)親の方々の中でも、どのような人がストレスや緊張を強く感じているのか、また家族への満足感が高いのかについて、いくつかの傾向が見えました。その中で比較的はっきりしていたのは、性別による違いです。もちろん、とくに男性の回答者が少ないので一般化は危険ですが、男性よりも女性の方が家族内のストレスを感じることが多く、逆に女性よりも男性の方が家族関係の満足度が高い傾向にありました。パートナーや子ども(継子を含む)との関係に悩んだり、家族内で負担を感じたりする頻度を総合した「家族内ストレス源」という指標得点の平均値で見ると、女性の方が高いことが図1のグラフからもわかります。
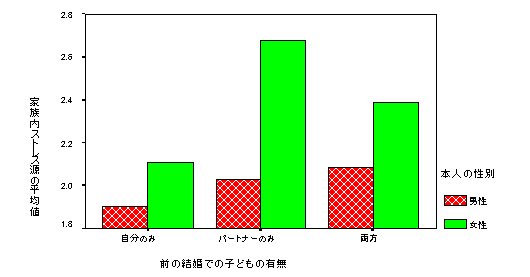
図1 男女別・前の結婚での子どもの有無別・家族内ストレス源
この図では、男女別だけではなく、前の結婚での子どもがカップルのどちらにあるかによっても、家族内ストレス源の高さを比較しています。ここからわかるのは、女性回答者の中でも、前の結婚での子どもが自分にはなくてパートナーのみにあった人がとくに頻繁に家族内の悩みや負担感を感じているということです。つまり、実母の経験がないのに継母になる経験をした女性がもっともストレスにさらされやすい状況にあることを示唆しています。このグループに含まれる女性は、家族関係満足度の点数ももっとも低くなっていました。
一方、家族内ストレス源や家族関係満足度は、パートナーとの関係からも影響を受けるようです。女性については、パートナーからの情緒的なサポート(相談、評価、助言)やパートナーとの同伴行動が多いほど、家族内ストレス源が低くなり、家族関係満足度が高くなる傾向が見られました。男性の場合は、パートナーとの葛藤(イライラさせられたり、文句を言われたり)が少ないほど、家族内ストレス源が減少するという傾向が顕著でした。男女の違いは興味深いところですが、いずれにしてもパートナーとの関係が家族内のストレスや満足感と深く関わっていることが示されています。
3.セメント・ベイビーのいる家族・いない家族
米国では、ステップファミリーに新しく生まれる赤ちゃんを「セメント・ベイビー」と呼ぶことがあるようです。セメント・ベイビーが誕生することが家族関係にどのような影響を与えるかについては米国の調査報告でもはっきりした結論は出ていないようです。今回の私たちの調査では、新しい子どもの誕生前と後の家族関係の変化について明らかにすることはできませんが、参考までにすでにセメント・ベイビーをもっている人とそうでない人とを比較してみました。図2は、男女別に、現在のパートナーとの間に子どもがあるかどうかによって、パートナーからの情緒的サポートの程度を比較したものです。
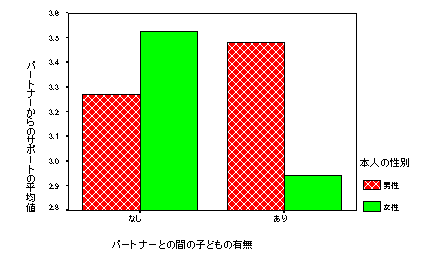
図2 男女別・パートナーとの間の子どもの有無別・パートナーからのサポート
このグラフを見ると、男性ではセメント・ベイビーがいるグループの方がパートナーからのサポートがやや高くなっています。ところが女性の場合は、逆にセメント・ベイビーのいるグループでサポートの平均値がめだって低くなっています。図には示していませんが、セメント・ベイビーのいる女性グループだけは、パートナーとの同伴行動の平均値もとくに低くなっていました。一方、セメント・ベイビーのいる人は、家族外の(親や親戚、近所や職場、元配偶者などとの)人間関係から生じるストレス源(悩み)が少ないという傾向も見られました。やはり、新しく生まれる子どもが家族の内外の人間関係に与える影響は単純なものではないようです。
4.専門機関からのサポート
これまでステップファミリーが専門機関からのサポートをどのように受けてきたのかについて、調査では、「親子関係、しつけ、教育問題など子育てに関する問題」「離婚再婚など夫婦関係を中心とする問題」「親権、養子縁組、養育権など親子関係を中心とする法律問題」「本人の悩みなど心理的ストレスや精神的健康に関する問題」の4つの相談項目に分けて、専門機関で相談を受けた経験について質問しました。結果として4項目とも、相談経験のある人は回答者の約 30~35%でした。しかし男女別にみると、全ての相談項目において、男性では相談経験のある人の割合は10%台にとどまっている一方で、女性は4項目ともほぼ4割の人が相談経験ありと答えています。特に「子育てに関する相談」では、男性回答者のうち相談経験があるとしたのは7%、一方、女性は41%が相談経験ありとしています。これは、ステップファミリーだけの傾向ではありませんが、やはり子育ての責任が女性の側にかかっていて、結果として女性が専門機関の相談を受けているという現状が伺える結果となっています。また男性の方が家庭内の問題を家族だけで解決しようと考え、外部の専門機関を利用することへの抵抗が強い傾向も伺えます。また相談方法では、訪問相談や電話相談とほぼ同じ割合で、相談経験者の4割程度の人がインターネットによる相談を利用しているのが特徴的です。
今後必要とする支援については、「学校など教育機関がステップファミリーへの理解を深めること」が第1位、「ステップファミリー専門の相談やカウンセリングの場を新たにつくること」が第2位、「児童相談所などの既存の専門機関がステップファミリーへの理解を深めること」が第3位という順で必要度が高いという結果になりました。
5.自由記述から -ステップファミリーの個々の声-
ステップファミリーとして普段難しいと感じる体験や、喜びや幸せを感じる経験などについて、調査では最後に自由に回答していただきました。大部分の回答者の方が記入してくださり、そこからは一人一人のステップファミリーの生の声が伝わってきました。内容的には、やはり難しさを感じる体験の方によりたくさんの記述がありました。全体をとおして、新しい家族の関係において、回答者のステップファミリーの方々はその親子関係に最も重点がおかれていて、その関係に悩み、ストレスを感じる一方で、新しい親子関係が築かれていくプロセスに喜びを感じていることが伺えました。少数ではありましたが、前の結婚での子どもとの面会などを通して、元のパートナーとの関係が一番難しいとする意見があったのも特徴的でした。中には、ステップファミリー歴30年という方から「現在は継子の孫も出来て、自然体で家族が暮らせています」という感想や、「自分自身が継子であったが、継母が愛情を注いで育ててくれた経験が、今のステップファミリーの基盤となっている」という意見もありました。
